はじめに「坂の上にある教会」

ポルトガルのポルトにある”ポルト大聖堂”に行ってきました。ポルトの街は地形の高低差が大きく、ポルト大聖堂は高い位置にあるため、坂道を登りながらアクセスしました。
さらにこの教会は13世紀に建てられており、市内で最も古い建物と言われています。
そんなポルト大聖堂の魅力は教会建築で分類される様々な様式、「ロマネスク、ゴシック、バロック」が見られるところにあります。
それでは、ポルト大聖堂について紹介していきたいと思います。
重厚感のあるロマネスク様式

ポルト大聖堂は13世紀に完成したロマネスク様式の建物です。そのため、建物にはロマネスクの特徴が色々と見られます。
まずバラ窓です。バラ窓は2本の塔の間にある窓に、バラの形を模してガラスが埋められているものです。

バラ窓
それは外から見た時はシンボル性が感じられます。
中では身廊の背部に当たるのですが、ステンドグラスから入るバラ窓の光は、重厚感のあるロマネスク建築に彩りを与えていました。

内側から見るバラ窓

ステンドグラスが華やかなバラ窓
13世紀に完成した後に度々改修を繰り返す教会ですが、このバラ窓はロマネスク様式としての当初の面影が残っている部分なのです。
次にヴォールト屋根です。
この教会は3廊式(身廊+側廊×2)になっているのですが、その3つともアプスの方に向かってヴォールトが伸びています。

身廊のヴォールト屋根

側廊のヴォールト屋根
そして、小さな窓です。
例えばゴシック様式では、大きなステンドグラスの窓が特徴的ですが、ロマネスク様式の窓は小さいのが特徴です。

ロマネスク様式に現れる小さな窓
その理由は構造にあります。ヴォールト屋根による水平力(スラスト)をこの窓が付く壁で受けているのです。
この建物の場合、構造的に窓が大きいと建物を支えることが出来なくなってしまいます。
それだけ構造的に重要な壁ということもあり、壁厚も大きいことが内部からも見て取れます。

窓周りから分かる大きな壁厚
先ほどゴシック様式の大きな窓を例に挙げましたが、ゴシック様式はロマネスク様式からのの脱却として生まれた様式であることを知っておくと理解しやすいと思います。
改築されたバロック様式のアプス

ロマネスクのヴォールト天井の奥にあるアプスは、どこか雰囲気が全体空間とは異なります。それもそのはず、このアプスはバロック様式です。
そのためグリッド状のヴォールトや彫像など、装飾で埋め尽くされているのが分かります。

バロック様式の天井

バロック様式の彫像
さらに、アプスとその横のチャペル(彫像が飾られている窪み部分)の間には様式が分かれる境界部分が見られます。

バロックとロマネスクが分かれる部分
チャペル側は建物としてはロマネスク様式ですが、チャペル内部はバロック様式となっているので、様々に混ざり合っていることも分かります。
これは17世紀中頃に改築されたもので、銀製の衝立はポルトガル人の芸術家によって作られたのです。
華やかなゴシック様式の回廊

教会の外には大きな回廊がありますが、これはゴシック様式のものです。
14世紀から15世紀にかけて作られたもので、尖頭アーチや交差リプヴォールトといったゴシックの要素が見られます。

回廊に現れる尖頭アーチや交差リブヴォールト
回廊の中央には中庭があるのですが、中に入るタイミングで雨が降ってきたことで面白いものが見られました。
2階に溜まった雨水が、動物の形をした樋から出てくる仕掛けになっているのです。
それはシンガポールのマーライオンのようで、観光客は皆写真を撮るのに夢中になっていました。

動物の口から雨が流れる

中庭の四周に同じような雨水処理の仕掛けがある
ポルトガルを象徴するアズレージョ

先ほどのゴシック様式の回廊には、ポルトガルの象徴とも言えるアズレージョが壁に貼られていました。

回廊に貼られているアズレージョ
アズレージョというのはタイルのことで、15世紀頃、イスラム文化の影響を受けてポルトガルに入ってきたものです。
ポルトガルでは、街中で装飾模様の施された青色のアズレージョをよく見かけますが、この教会ではタイル全体で一つの絵画となるような装飾となっていました。

絵画のように表現されるアズレージョ
おわりに「教会の様式を学べる場所」

以上、ポルト大聖堂の紹介でした。これだけ様式がミックスされた教会はなかなか無いので、非常に価値のある場所だと思います。
教会建築を学んでいても様式ごとの違いを覚えるのは少し大変ですが、このポルト大聖堂は見た目も面白く、楽しく学ぶことができると思います。
ポルトに行ったらぜひ寄ってみることをおすすめします。
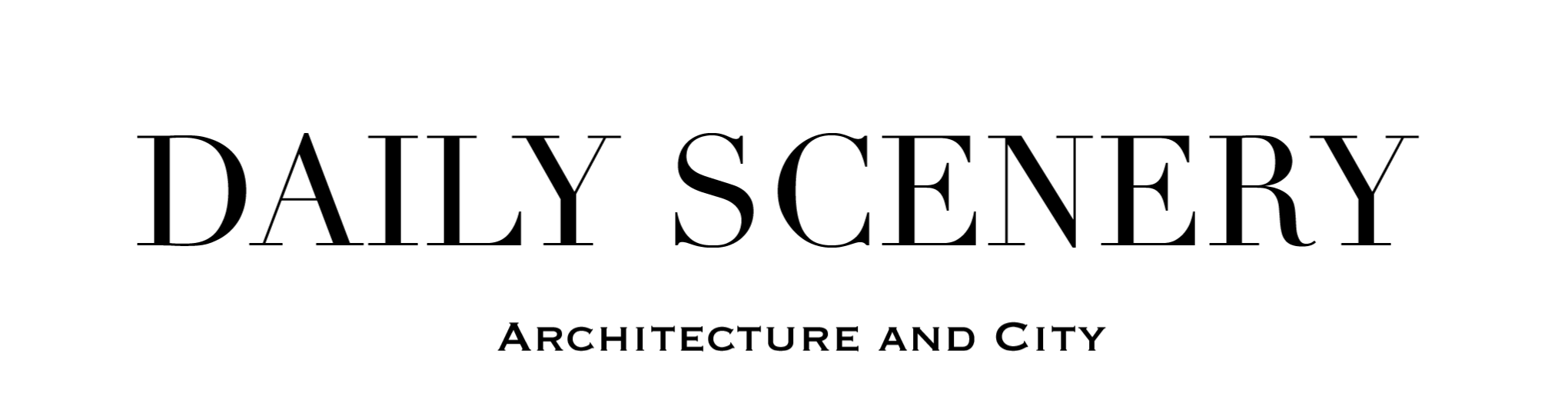



後にゴシック様式の時代になると、フライングバットレスという水平力を伝達する部材が登場するので、窓は大きく開けられるようになります。